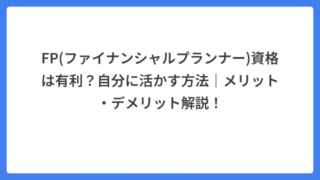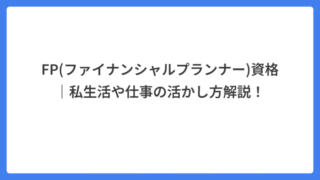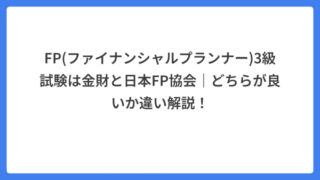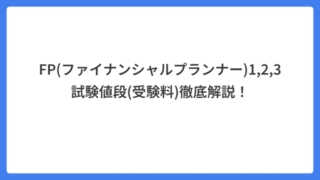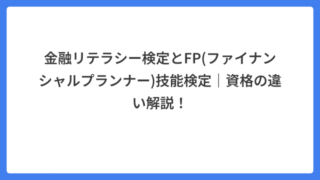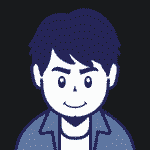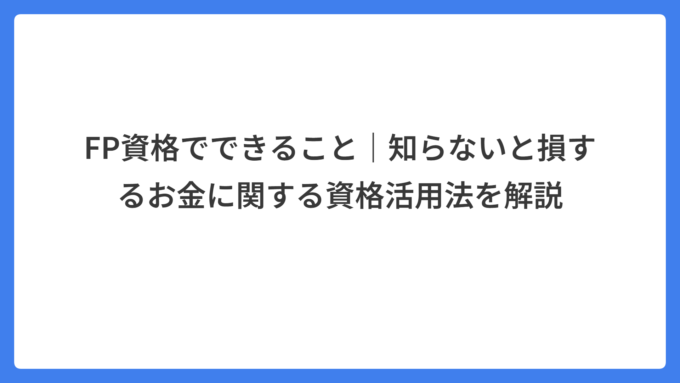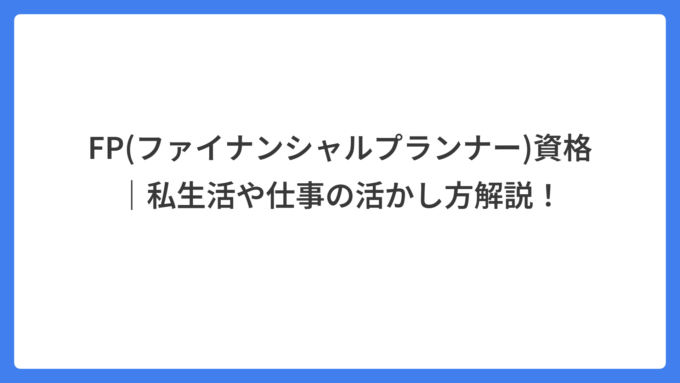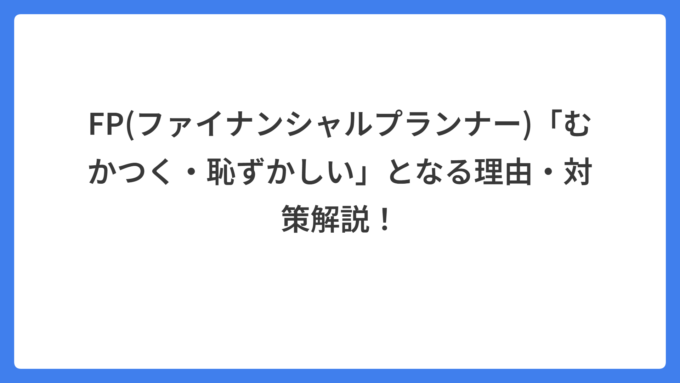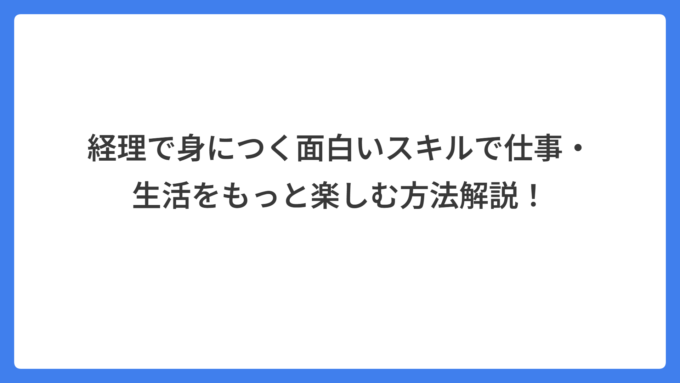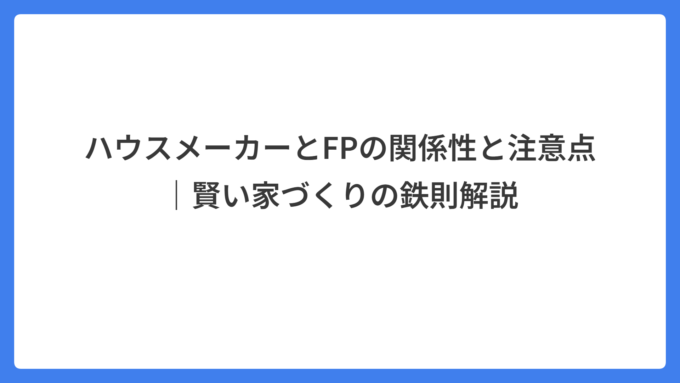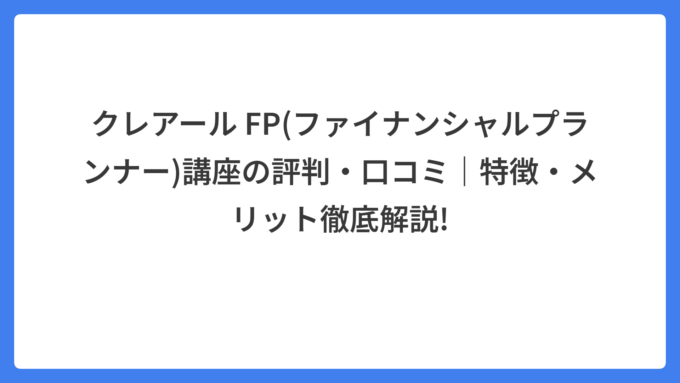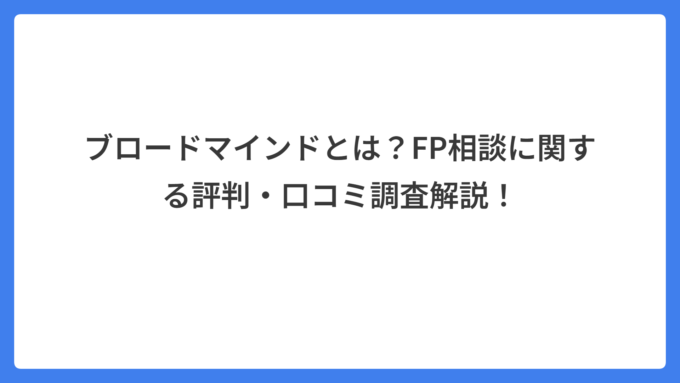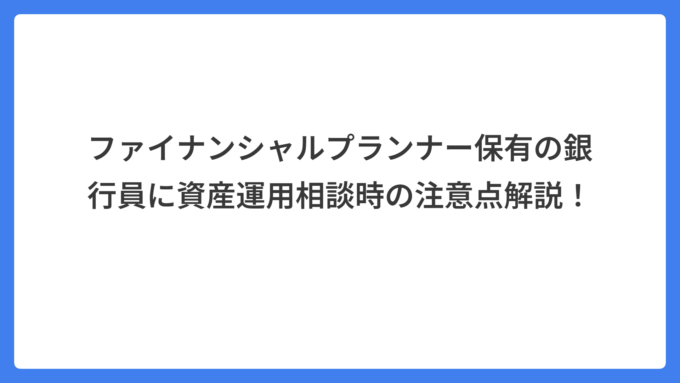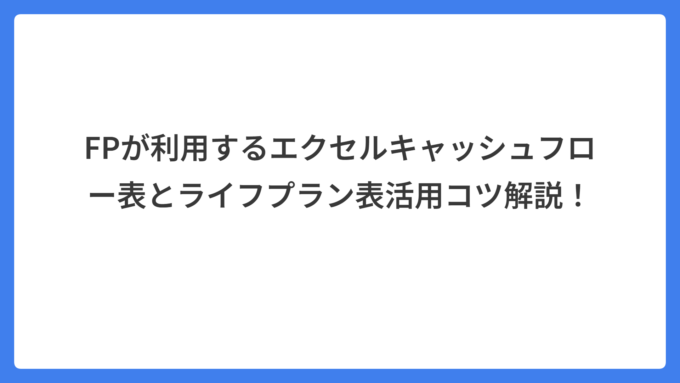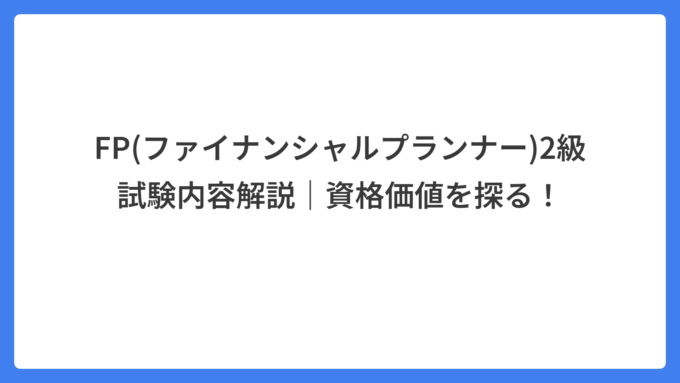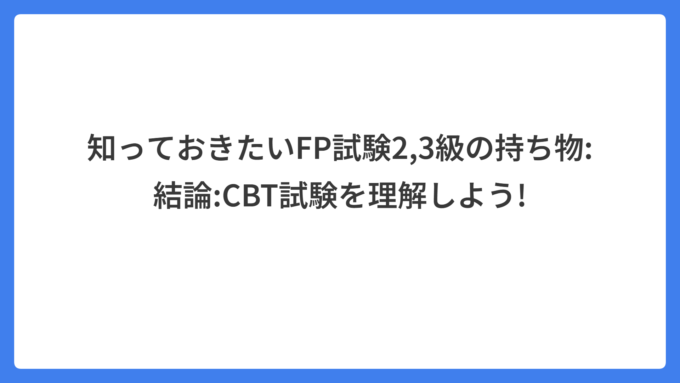金融リテラシー検定とFP(ファイナンシャルプランナー)技能検定|資格の違い解説!
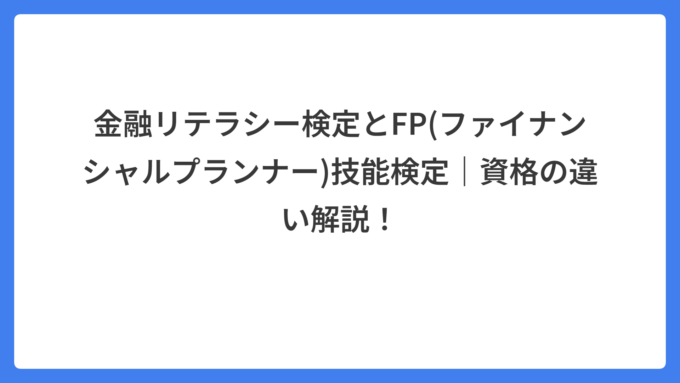
お金や金融の知識をきちんと身につけて、人生のライフプランや家計管理に自信を持ちたいあなたへ。
最近は「金融リテラシー検定」や「FP(ファイナンシャルプランナー)技能検定」といった検定・資格への注目が高まりつつあります。
2022年に成人年齢の引き下げで金融教育にも近年、焦点が当たっています。
金融リテラシー検定はそういった時代背景のもと、創設された検定です。
でも、それぞれ試験の内容や目的、合格率、勉強方法、活躍できる場にはどんな違いがあるのでしょうか?
この記事では、金融リテラシー検定とFP資格について、特徴や受験資格、学習方法、合格後の活用シーンなどを分かりやすく解説します。
はじめて資格取得や金融の知識習得を考えている方も、比較しながら自分に合う道を見つけられるよう、両方のメリット・デメリットにも触れていきます。
どちらを選ぶべきか迷っている方は、ぜひ読んでみてください。
金融リテラシー検定とFP(ファイナンシャルプランナー)技能検定の違い
金融リテラシー検定とFP(ファイナンシャルプランナー)資格は、
どちらも金融教育を受けた人が持つ重要な資格や知識を示します。
しかし、その目的や試験内容、対象者が異なります。
金融リテラシー検定は、一般社団法人金融財政事情研究会(金財)が主催するもので、より広範囲な金融リテラシーの向上を目指しており、高校生から新社会人まで幅広い層に適しています。
一方、FP(ファイナンシャルプランナー)資格はとくに実践的なスキルと知識が要求される国家資格で、個別のライフプランに基づく資産形成や保険、税金についての深い理解が求められます。
FP技能検定を主催している団体は、日本FP協会と金財の2つです。
とくに級数が上がるほど金融業界、不動産業界などでは重宝される資格でもあります。
主に金融リテラシー検定とFP3級を比較していきます。
引用:金融リテラシー検定 | 一般社団法人 金融財政事情研究会
金融リテラシー検定の目的
金融リテラシー検定の目的は、広く一般の人々が金融に関する基本的な知識を持つことです。
教育の場で習得しづらい金融知識を手軽に学ぶ機会を提供し、お金の管理に役立つリテラシーを高めることを狙っています。
家庭での生活や資産形成において必要な知識を備えることで、より良い経済的な意思決定ができるようになります。
それに対し、FP資格取得の目的は、個人や法人に対してファイナンシャルプランニングの専門知識を提供することであり、多くのケースで活用される具体的なスキルを身につけることにあります。
金融リテラシー検定を創設
学習指導要領の改訂により、2022年4月から高校教育における金融経済教育の内容が拡充されました。また、2022年4月の成年年齢の引下げに伴い、資産形成だけでなく、契約や金融トラブルに関する教育の必要性がより一層求められています。しかしながら、金融経済教育についてインプット型のセミナーは増加しているものの、知識や理解のアウトプットを測定する機会は少ないのが現状です。そこで体系的かつ実用的な金融知識と適切な判断力の向上を企図し、一般社団法人金融財政事情研究会はこのほど、高校生、大学生、新社会人などを対象とした金融リテラシー検定を創設します。
FP3級の関連記事はこちらをごらんください:FP(ファイナンシャルプランナー) 3級試験は簡単?押さえたいポイント解説!↗,FP(ファイナンシャルプランナー)3級試験は金財と日本FP協会|どちらが良いか違い解説!,FP(ファイナンシャルプランナー)1,2,3試験値段(受験料)徹底解説!
| 試験団体 | 金融リテラシー検定 | 日本FP協会 FP3級 | 金融財政事情研究会FP3級 |
|---|---|---|---|
| 試験方式 | IBT(Internet-BasedTesting)方式 ※パソコンやスマートフォン、タブレット等で、いつでもどこでも受験できる試験 | 2級・3級の学科試験及び実技試験は、原則としてCBT(Computer Based Testing)方式で実施 ※テストセンター・受験期日を選択 | 2級・3級の学科試験及び実技試験は、原則としてCBT(Computer Based Testing)方式で実施 ※テストセンター・受験期日を選択 |
| 受験可能期間 | 試験申込後180日以内 | 休止期間を除き、テストセンターの空いている日時から選択可能 | 休止期間を除き、テストセンターの空いている日時から選択可能 |
| 試験の対象者・受験資格 | 高校生、大学生、新社会人など ※受験資格は特にありません。 | FP業務に従事している者または従事しようとしている者(FP業務とは、資産の設計・運用・管理およびこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務をいいます) | FP業務に従事している者または従事しようとしている者 |
| 試験時間 | 40分 | 学科試験90分 実技試験60分 | 学科試験90分 実技試験60分 |
| 出題形式 | 正誤問題35問、三答択一式15問 | (学科)多肢選択式60問、 (実技)多肢選択式20問 | (学科)○×式 三答択一式60問、 (実技)事例形式5題 |
| 合格基準 ※表の試験はすべて6割以上 | 100点満点で60点以上 | 36点以上(60点満点)、 60点以上(100点満点) | 36点以上 (60点満点)、30点以上 (50点満点) |
| 受験手数料(税込) | 合計3,300円 | 合計8,000円 | 合計8,000円 |
| 公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
引用:2級・3級FP技能検定(CBT試験) | 日本FP協会↗,2級・3級FP技能検定 試験要綱 | 日本FP協会,ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験科目及びその範囲 | 一般社団法人 金融財政事情研究会↗
金融リテラシー検定とFP試験の試験内容比較
金融リテラシー検定では、基本的な金融知識から始まり、投資、保険、税金といった分野の内容を含む試験が行われます。
日常の生活に密着した問題が多く、カジュアルに受けられるため特に高校生や大学生に人気です。
難易度レベルはお金の知識の入門編といった所です。
・実際の金融リテラシー検定テキストサンプル:
・実際の金融リテラシー検定試験問題サンプル:
https://www.kinzai.or.jp/uploads/literacy_mondai_0123.pdf
一方、FP試験では、ライフプランニングやリスク管理、金融資産運用といった専門的な内容が中心で、非常に実践的です。
合格するためには、深い理解と計画的な勉強方法が不可欠で、受験者の多くが過去問を活用して準備を進めます。
金融リテラシー検定・FP資格それぞれの対象者
金融リテラシー検定は、多くの人が参加できるように設計されています。
とくに高校生や大学生、新社会人にとって、リテラシーを高め、将来の金融生活を安定させるために役立ちます。
FP資格は、金融機関で働く人や、独立してFP(ファイナンシャルプランナー)を目指す人々を対象としています。
とくに、資産運用や保険、年金などの分野で活躍することを希望する人にとっては、必須の資格と言えるでしょう。
金融リテラシー検定・FP資格それぞれの合格率
金融リテラシー検定の合格率は比較的高めで、多くの受験者が一度で合格を果たしています。
これは、試験が基礎的な内容にフォーカスしているためであり、受験者の年齢や職業を問わず、多くの人が受検することができる点も関係しています。
一方、FP試験の合格率はやや低く、国家資格ということもあり、専門的な知識を問われるため、しっかりとした対策が必要です。
過去問題を使った勉強方法や実践的な模擬試験が推奨されています。
将来のキャリアパス
金融リテラシー検定を取得することで、金融機関や一般企業、教育機関での活動においてベースの金融知識を持つことが証明されますが、それ以上の専門的な資格取得の道へ進むことも可能です。
一方、FP資格は、具体的なキャリアパスを開く切符となり、金融コンサルタントや独立系アドバイザーとしての活躍が期待されています。
金融知識の深さは、自信を持ってお客様に金融商品の説明や資産形成のプランニングを提供するのに役立ちます。
次の項でさらに細かく金融リテラシー検定について解説していきます。
金融リテラシー検定とは
金融リテラシー検定は、とくに若年層を中心に幅広い層に金融知識を提供するために作られた検定です。
金融の基本的な仕組みから資産形成、投資、税制までの内容が含まれるため、受検者にとっては日常生活での金融的な意思決定を支援するツールとなります。
制約が少なく、比較的安易に受検できるため、金融教育の初歩や役に立つ知識の習得を志すすべての人にとって有意義です。
金融リテラシー検定の概要
金融リテラシー検定は、金融教育の普及を目指して、一般の人々や学生が参加できる検定です。
試験はIBT(インターネット・ベースド・テスティング)形式で行われ、日本全国どこからでもアクセス可能です。
内容は実生活での金融取引や契約に関する基礎から始まり、投資信託や保険などの知識を問われます。
この検定を通じて、日常生活に役立つ基本的な金融の知識やスキルを広く習得することができます。
例えば、大学生や社会人で一人暮らしを経験する際に、お金に関するトラブルに見舞われることもあります。
金融リテラシー検定を学ぶ人は、FP資格ほど難しくはないので、お金に関する知識を学びつつ、お金に関する守る力を高めることができます。
金融知識の基本
金融リテラシー検定では、銀行口座の開設からクレジットカードの利用、さらに投資信託や保険の基本的な仕組みまでを理解することが求められます。
これらの知識は、一見難しそうに思えますが、居住環境や社会全体の金融システムを理解するための重要なステップです。
基礎的な金融知識を習得することで、自分自身の資産をより効果的に管理し、将来の経済的な不安を軽減させることができるでしょう。
基本的なスキルセット
金融リテラシー検定を通じて身につけるべきスキルセットは、金融商品やサービスの基礎的な知識を理解し、個人の生活やライフプランにどのように活用できるかを判断する能力です。
また、自分自身の資産状況を把握し、それに基づいて適切な資産形成を行う基本的なスキルも含まれます。
これらのスキルを持つことで、日々の消費や資産運用の際に、より効果的な意思決定が可能となります。
金融リテラシー検定の準備方法
金融リテラシー検定の準備には、指定のURLから公式テキストや関連する動画教材を活用するのがおすすめです。
とくに、実際の問題形式を把握するために過去問に取り組むことが効果的です。
また、高校の学習指導要領に沿った内容も多く含まれているため、学校での金融教育と併せて学習することが有用です。
インターネットでの試験となるため、コンピューターの基本的な操作に慣れておくことも重要です。
試験開催日と場所
金融リテラシー検定は、IBT方式により、全国どこからでも参加できる試験です。
公式サイトにて申込み手続きを行うことで、試験申込後180日以内であれば自宅などの環境で受験可能です。
受験の日程は随時公式サイトで確認でき、自分のスケジュールに合わせて計画的に受験できる点が特徴です。
受験方法や関連する問い合わせについては、すべて公式ホームページで対応が可能です。
金融リテラシー検定は、受験料もFP資格に比べると3,300円と安いです。
とくにお金に関する知識を学ぶことに少し抵抗を感じる人が、興味をもつきっかけになるような検定です。
お金の知識の入門と言う形で学んでみるのも良いでしょう。
引用:金融リテラシー検定 | 一般社団法人 金融財政事情研究会
- 金融リテラシー検定とFP技能検定3級の主な違いまとめ
- 金融リテラシー検定(金融財政事情研究会)
・IBT方式(インターネット環境があればどこでも)
・難易度 お金の知識の入門レベル
・試験日 申込後 180日以内
・受験料合計 3,300円
・試験時間合計 40分
・試験科目 金融リテラシー検定
・知名度 FP(ファイナンシャルプランナー)技能検定より低い
・金融知識の専門性 低い
FP技能検定3級(日本FP協会・金融財政事情研究会)
・CBT方式(テストセンターにて)
・難易度 金融リテラシー検定より範囲が広い
・試験日 休日を除く指定日
・受験料合計 8,000円
・試験時間合計 150分
・試験科目 学科・実技試験
・知名度 金融リテラシー検定より高い
・金融知識の専門性 高い
FP(ファイナンシャルプランナー)技能検定の資格とは
FP(ファイナンシャルプランナー)とは、個人や法人に対して資産運用や保険設計、相続対策などを行う専門家で、金融の側面からトータルライフプランを提案します。
資格取得により、証券、保険、銀行業務など、幅広い領域で活躍する道が開かれます。
FP(ファイナンシャルプランナー)技能検定は国家資格であり、試験に合格するためには金融商品全体の理解と、実務で役立つ応用的な知識が求められます。
不動産や税金、年金に関する知識も不可欠です。
FP(ファイナンシャルプランナー)の役割
FP(ファイナンシャルプランナー)の役割は、顧客のライフプランに基づいて、最適な資産管理や運用の方法を提案することです。
具体的には、家計の見直しや保険の選定、住宅ローンの計画、不動産投資、年金や相続の対策などです。
FP(ファイナンシャルプランナー)は、お客様の生活に関する財務アドバイザーとして、詳しい知識と専門性を活かし、長期的な視点での資産形成をサポートし、経済的な安心を提供します。
FP(ファイナンシャルプランナー)資格の種類
FP資格には、国家試験である「ファイナンシャル・プランニング技能検定」と、民間資格である「AFP」(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)や「CFP」(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)などがあります。
技能検定は3級から1級まであり、とくに2級以上がプロ向けです。
AFPやCFPは、国際的にも認知されており、とくにCFPは高度な専門知識を証明する資格として知られています。
FP(ファイナンシャルプランナー)技能検定の試験内容
FP技能検定の試験では、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継など、多岐にわたる分野から出題されます。
試験には学科試験と実技試験があり、どちらも合格することで資格取得となります。
実技試験では、ケーススタディに基づいた現実的なシナリオに対するアドバイス能力が問われます。
これにより、幅広い金融知識の実際の活用が期待されます。
FP(ファイナンシャルプランナー)の職業としての展望
FP(ファイナンシャルプランナー)は、金融業界全体で需要が高い職業です。
銀行、保険会社、証券会社などの金融機関だけでなく、独立したアドバイザーとして個人の顧客を持つこともできます。
信頼性の高いキャリアパスを提供するこの資格は、経済状況の変化にも柔軟に対応できるため、将来的な展望が明るいとされています。
とくにライフプランに基づく資産の最適化が求められる今、FP(ファイナンシャルプランナー)の専門性は非常に貴重です。
FP(ファイナンシャルプランナー)になるための学習方法
FP資格を取得するには、専門学校や通信講座、eラーニングを活用した学習方法があります。
多くの受験者が公式テキストや過去問に取り組み、学習を進めています。
また、試験に必要な広範な知識を体系的に学ぶためには、高校や大学での経済学や商学の基礎が役立ちます。
実務経験を持つことが大きなアドバンテージとなるため、求人情報を利用して実践的な知識を得ることも非常に有益です。
金融リテラシー検定とFP(ファイナンシャルプランナー)技能検定の試験形式
金融リテラシー検定とFP(ファイナンシャルプランナー)技能検定の試験形式には、いくつかの違いがありますが、どちらもインターネットベースまたはペーパーテストで行われます。
金融リテラシー検定は、日常生活で必要な金融知識を問うのに対し、FP試験は専門的なスキルと知識を必要とします。
どちらの試験も、試験日は固定されておらず、IBT試験かCBT試験にて実施、多くの受験者が参加しています。
※FP2,3級はCBT方式、FP1級はペーパー形式での試験です。
受験者のニーズに合わせた試験形式が提供されています。
試験の形式と時間
金融リテラシー検定は、インターネットを通じて実施されるIBT形式で、制限時間内に所定の数の問題を解く形です。
主に選択問題で構成されており、日常の金融知識を確認する内容です。
FP(ファイナンシャルプランナー)試験は2,3級はCBT方式、
1級はペーパーテストで、学科試験と実技試験の2部構成となっています。
学科試験は主にマークシート形式で、
実技試験はケーススタディをもとにした問題(事例形式)が多いのが特徴です。
試験時間は各試験で異なるため、事前に確認が必要です。
資格の受験費用
金融リテラシー検定の受験費用は、比較的低価格で、多くの受験者が気軽に受験できる設定となっています。
一般社団法人金融財政事情研究会の公式ページで詳細が公開されています。
FP試験の受験費用は、技能検定の等級によって異なりますが、こちらも公的機関が実施しているため信頼性があります。
受験費用は、検定や試験を受ける日程や会場によって変動することもあるため、最新の情報を事前に確認することをおすすめします。
合格基準
金融リテラシー検定の合格基準は、100点満点で60点以上で合格と判断され、基準得点を上回る必要があります。
FP試験は、学科試験、実技試験の両方で合格点に達することが必要です。
とくに実技試験では、実践力が重視されるケーススタディ形式が多く、自分の回答が現実のシナリオでどれだけ通用するかが試されます。
試験の難易度
金融リテラシー検定は、日常生活に役立つ知識を問うため、比較的簡単と感じる受験者も多いですが、しっかりとした準備がないと合格は厳しいとされています。
一方、FP試験は、非常に専門的な知識が問われるため、難易度が高いとされています。
とくに2級以上の試験は資産運用や保険、税制についての深い理解が必要です。どちらの試験も過去問をしっかりと復習し、試験形式に慣れることが合格への近道です。
過去問題について
金融リテラシー検定やFP試験では、過去問を使った学習が非常に効果的です。
金融リテラシー検定では、問題の傾向を掴むために過去問から出題の意図を理解することが可能です。
FP試験では、実際の問題パターンをしっかりと把握し、事前に模擬試験を実施することが推奨されています。
各種の教育団体や公式サイトでは、過去問が公開されているため、受験する前に必ず確認しておきましょう。
試験の申込み方法
金融リテラシー検定の受験申込みは、公式ウェブサイトを通じてオンラインで行います。
IBT方式を利用して、決済もネット上で完了するため、手間が少なく参加しやすいのが特徴です。
FP試験の申込みは、指定された試験機関のウェブサイトから行います。受験資格や期日があるため、申込み時にはこれらを確認することが大切です。
どちらの試験も受験票が必要となるため、発行の手続きは早めに行いましょう。
金融リテラシー検定とFP(ファイナンシャルプランナー)資格のメリット・デメリット
金融リテラシー検定とFP(ファイナンシャルプランナー)の資格は、どちらもそれぞれのメリットとデメリットがあります。
金融リテラシー検定のメリットは、日常生活に密着した金融知識を幅広く学べる点です。
そして、FP資格の一番のメリットは、専門的な知識を活かしてプロのアドバイザーとしての活動が可能になることです。
自身のキャリアパスやスキルアップを考慮し、どちらを選ぶかを慎重に判断することが重要です。
金融リテラシー検定のメリット
金融リテラシー検定のメリットは、何といっても気軽に受けられることです。
時間や場所に縛られず、どこでも受験可能で、短時間で完了します。日常生活における金融知識をしっかりと身につけることができ、今後の資産形成や買い物、契約などで役立ちます。
幅広い層が受検可能なため、お金の知識の入門として貢献します。
金融リテラシー検定のデメリット
一方で、金融リテラシー検定のデメリットとしては、資格としての専門性や認知度がそれほど高くないことが挙げられます。
金融機関での専門職を目指す場合、この資格だけでは不十分とされることが多いです。
また、検定の内容が基礎的なため、あまり深い知識を求めている人には物足りないかもしれません。
一度学んだとしても、知識を実践に移す機会が乏しいと、検定の意味がないと感じることがあります。
FP(ファイナンシャルプランナー)資格のメリット
FP資格の最大のメリットは、専門職としての地位を確立できることです。
お金に関する総合的な知識を身につけるこの資格は、金融業界だけでなく幅広い職種でのキャリアのステップアップに繋がります。
3級取得後は、2級、1級、AFP、CFPといった専門性をよりお金に関する知識を高めることができます。
とくに、資産運用や保険、税金など専門的な分野での活躍が期待されるため、職場での存在感を強めることができます。
資格を持つことで、顧客に信頼されるパートナーとしての信頼性も向上します。
FP(ファイナンシャルプランナー)資格のデメリット
FP資格のデメリットは、取得までの時間と労力がかかることです。
試験自体が難しく、十分な勉強が必要であり、合格には実践的な理解と深い知識が要求されます。
また、受験料や講座料がかさむことも、資格取得の負担になります。
そして、資格を持っていても実際のビジネスで活用するには、経験と信頼が必要となるため、すぐに大きな効果が得られるわけではありません。
どちらを選ぶべきか
どちらを選ぶべきかは、あなたのキャリア目標や生活スタイルに基づきます。
金融リテラシー検定は、手軽に金融の基礎を学び、日常生活で生かしたい方に理想的です。
一方、FP資格は、専門的な知識とスキルを認定してプロとして働きたいと考えている方に向いています。
それぞれの資格のメリットとデメリットを考慮し、自分に最適な選択をしてください。迷ったら、身近な専門家に相談するのも一つの方法です。
どちらを選べばいいかのアドバイス
金融リテラシー検定とFP資格は、それぞれのゴールに応じた選択が重要です。
金融リテラシー検定は、生活や仕事の基本的な金融理解が目的で、自分の経済生活をより良いものにしたい人に適しています。
とくに高校生、大学生であれば、未知の領域を勉強する入門的なものになるでしょう。
ただ知名度という点では、まだまだな面が正直あります。
一方、FP資格は、金融業界での専門職を目指す人や、アドバイザリー業務を志望する人に向いています。
金融リテラシーに比べて、目指す級にもよりますがFP資格の難易度は高くなります。
その分、より専門性の高いお金の知識が身についていることを証明できます。
望む業種で、FP資格が必要になる場合は、公私とともにFP資格は、活かす場面が多くなり活躍ができます。
どちらにしても、まずは自身の興味やキャリアビジョンを明確にし、それに基づいた決断を行うことが成功への鍵です。
FP(ファイナンシャルプランナー)に関する関連記事